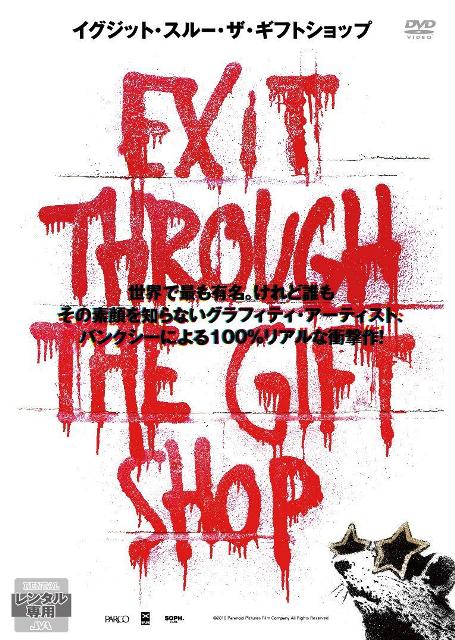僕よりも面白いから・・・一つの〈教訓〉になるかもしれない」
冒頭、顔を隠し、声を変えたバンクシーが「この映画」について語る。グラフィティ・アーティストとして、イギリスを中心に名を馳せるバンクシー。その正体はずっと不明だった。不明だったが、多くのアシスタントがいて、次々に「作品」が出現しては翌日には消され。そんなアートがオークションでは高値で売れる。出版された本も世界中でベストセラーになる。ちなみに我が家には本はもちろん、カレンダーまである(笑)
そんな謎のアーティスト、バンクシー。まずこの映画の驚きは、バンクシーが実際に夜の街でグラフィティする場面がカメラにおさまっていること。夜の誰もみていないところで「造り上げて」、翌朝の反応があって、すぐに消されるという宿命の中で、記録として残しておくこともいいか、、、と。バンクシーにそう思わせた男が、この映画の主人公・ティエリーだ。
彼は、ビデオマニア。自分では記録を残す中毒だと言っている。フランスからロサンゼルスに移り住んで、古着屋を経営。家族と暮らしながら、日々ビデオを撮る。幼い頃、母を亡くした。その瞬間・瞬間は帰ってこない。だから、残しておく。記録として。
そんな男がストリート・アートに出会うのはフランスに里帰りしたとき。いとこのミスター・インベーダーの活動を追ったこと。好きなモノを描いて、好きなところにはりつける。その行為に興味を持つ。ティエリーは、インベーダーだけでは飽きたらず多くのストリート・アーティストを追う。カメラを構えること「普通」となり、相手にカメラを向けられていることを普通に思わせる彼の得意技、普段、人の目を避けている人たちを記録として残していく。
ある日、シェパードとの出会い。オバマの肖像画で有名になった彼の後をカメラをもって追いかけるティエリー。シェパードは、その「半端なさ」に心を許していく。どんなところへもついてくる。何時まででもついてくる。そして、見張り役になる。
ストリート・アートを追いかける中で、ティエリーがバンクシーに行き着くのは必然だろう。それほどまでにバンクシーの名は知れている。どうにかしてバンクシーに会いたい。そう思うティエリーだが、もちろんなぞの男にそうそう簡単には出会えない。
ある日、ロサンゼルスに行こうとしたバンクシーが、インベーダーを通じて紹介してもらった人物、ロサンゼルスの「壁」を知り尽くした男、それがティエリーだった。そして、バンクシーのロサンゼルスでの活動の案内役をかってでる。そのティエリーの態度と対応にバンクシーも気を許す。
次の日には姿を消すことの多い作品。それを記録として残しておくのも悪くない。ティエリーになら、それが許せる。そう思わせた。バンクシーのアシスタントは「とても驚いた」とインタビューで応えている。
映像をためにためたティエリー。なぜ撮るのか? そんな質問に窮して映画をつくるため、と応え、それを本当にやってのこる。「LIFE REMOTE CONTROL」と名付けられた作品を作る。それを見たバンクシーは、落ち着きのない人物がチャンネルを次々変えるような作品。確かに、統一感もなければ主張もない。そんな作品だった。バンクシーはその時に思ったのかも知れない。ティエリーは面白い、と。
アートを追いかける彼に、自分でアートをしてみればどうか。そういったバンクシーも、その後のティエリー、いやMBWを予想していなかったという。
ティエリーはミスター・ブレインウォッシュという名で、ロサンゼルスで有名な「アーティスト」になる。バンクシーから簡単な推薦状をもらい、それを地元の大手出版社が大々的に取り上げ、そうして「個展」が成功する。
一人のビデオマニアの執着心が生んだ出口、いろんな土産を探りながら出たところは「アーティストとしての自分」だった。
これは完全なるドキュメンタリー映画だ。謎の大物グラフィティ・アーティスト、バンクシーをスタイリッシュに、なんというか研ぎ澄まされた映像と構成で追うものではなく、なんとも泥臭く、ちょっとコミカルに描くアート作品。その絶妙なバランスが、見終わったときに「おもしろかった」と思わせる。
今まで、ちょっと見なかった普通の男を取り巻くシンデレラストーリー、そんなタイプの作品だ。
→ CinemaSに戻る